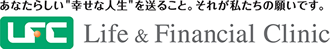ChatGPT(生成AI)を活用したライフイベントの整理と貯蓄計画、保険見直しの具体的な方法

教育費や老後資金、介護費用など、人生にかかるお金への不安をChatGPT(生成AI)でスッキリ整理!本記事では、ライフイベントの時系列整理、必要資金の試算、税制優遇制度の活用、保険の見直し、家計全体のバランスシート作成までを5ステップで紹介。お金の流れを“見える化”することで、「今やるべきこと」が明確になり、安心して未来に備えるための行動につなげられます。
「なんとなくの不安」を「具体的な見通し」に変えるには?
子どもの教育費、住宅購入の資金、そして老後の生活費…。人生にはまとまったお金が必要となる「ライフイベント」がいくつも訪れます。
しかし、それぞれのイベントに対して「いくら必要なのか?」「いつまでに準備すべきか?」「どのような手段で備えるべきか?」といったことを、きちんと整理して把握できている人は意外と少ないのが現実です。
さらに多くの方が、貯蓄・投資と保険の“ちょうどいいバランス”に悩んでいます。
- 今入っている保険、本当に自分に必要?
- 教育資金と老後資金、どちらを優先すればいい?
- 貯金はしてるけど、具体的にどう貯めていけばいいのかは分からない…
こうした悩みは、誰にでもあるものです。ですが、そのままにしておくと、「漠然としたお金の不安」から抜け出せなくなってしまいます。
そんなときに役立つのが、ChatGPTを使ったライフイベントとマネープランの“見える化”です。対話形式で将来を整理し、必要な資金や保障を洗い出すことで、「今やるべきこと」が自然と明確になります。
ChatGPT(生成AI)でつくる、将来に備える5つのステップ
将来に向けたお金の準備と聞くと、難しく感じるかもしれません。ですが実際には、ChatGPTと一緒に5つのステップを進めていくと、ライフイベントに備える貯蓄・運用・保障の戦略が自然と整っていきます。
「どこから始めたらいいかわからない…」という方こそ、このステップを参考にしてみてください。ChatGPTと対話を重ねることで、将来の見通しが少しずつクリアになり、不安が自然と安心に変わっていくことでしょう。
ステップ1:ChatGPTにライフイベント一覧表を作ってもらう
―「未来のお金の予定表」を時系列で“見える化”する―
最初のステップは、これから訪れるライフイベントを具体的に整理することです。「教育費や住宅ローン、親の介護、老後資金……いずれ必要だとは思っているけれど、正直いつ・いくらかかるのかは曖昧」という方は少なくありません。
でも、何にいつ備えるべきかが見えなければ、貯蓄や投資、保険の選択も正しい判断ができなくなります。そこで役立つのが、ChatGPTによる「ライフイベントの時系列整理」です。
あなたの家族構成や年齢、住宅ローンの残り期間、両親の年齢など、現在の状況をChatGPTに伝えるだけで、10年・20年先までの主要イベントを一覧化してくれます。
ChatGPTへの依頼例(プロンプト)
私たち夫婦の今後のライフイベントを時系列で整理し、それぞれのイベントにかかるおおよその資金を一覧化してください。 ▼前提情報 ・夫:35歳、会社員 ・妻:34歳、パート ・子ども:5歳(幼稚園) ・住宅ローン:残り25年 ・両親:70歳と68歳(将来の介護の可能性あり) ・老後は65歳退職予定
ChatGPTの出力例(ライフイベント一覧)
1年後:子どもの小学校入学 → 約10万円 7年後:中学校入学 → 約15万円 10年後:高校入学+学費(3年間)→ 約140万円 13年後:大学進学 → 約370万円 5年後以降:両親の介護費用(3年)→ 約540万円 15年後:自宅リフォーム → 約200万円 30年後:老後資金 → 最低3,000万円
計画は「未来を知ること」から始まる
未来のイベントを“見える化”すると、「何となく不安だったこと」が、「いつ・いくら・どう備える?」という行動に変わるきっかけになります。ここで整理した情報は、このあとの「資金計画」「貯蓄配分」「保険の見直し」のすべての土台になります。
ChatGPTを使えば、抜け漏れなく、客観的に将来の支出イベントを並べてくれるので、自分一人で考えるよりもずっとスムーズ。このステップだけでも、「やるべきこと」が明確になり、家計管理の視界が一気に開けていくのを実感できるはずです。
次は、こうして整理したライフイベントに対して、「いくら・いつまでに貯めるべきか」をChatGPTと一緒に設計していきましょう。
ステップ2:必要資金の一覧と積立目安を出してもらう
―「いくら必要か?」を明確にして、貯蓄のペースを見極める―
ステップ1で将来のライフイベントを洗い出したら、次はそれぞれのイベントに対して「いつまでに」「いくら必要か」を数値で整理していきましょう。
このステップの目的は、将来の出費に備えるために、どれくらいの期間で、どのくらいの金額を準備する必要があるかを具体的に知ることです。これがわかれば、「とにかく貯金」から脱して、計画的な積立ペースを設定できるようになります。
もちろん、ここでもChatGPTに頼ればOK。イベントごとの必要時期と金額を入力すれば、単純計算で毎月の積立目安を一覧にしてくれます。
ChatGPTへの依頼例(プロンプト)
先ほどのライフイベント情報を元に、 ・いつまでに ・いくら必要か ・毎月の積立額はいくらか を一覧表にしてください。
ChatGPTの出力例(必要資金一覧と積立目安)
| イベント | 必要時期 | 金額 | 準備期間 | 月額積立目安 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校入学 | 1年後 | 10万円 | 12ヶ月 | 約8,400円 |
| 中学校入学 | 7年後 | 15万円 | 84ヶ月 | 約1,800円 |
| 高校入学+学費 | 10年後 | 140万円 | 120ヶ月 | 約11,700円 |
| 大学進学+学費 | 13年後 | 370万円 | 156ヶ月 | 約23,700円 |
| 介護費用 | 5年後 | 540万円 | 60ヶ月 | 約90,000円 |
| 自宅リフォーム費 | 15年後 | 200万円 | 180ヶ月 | 約11,200円 |
| 老後資金 | 30年後 | 3,000万円 | 360ヶ月 | 約83,400円 |
※あくまで「単純割り算」の目安です。積立NISA・iDeCoなどの運用利回りを考慮すれば、必要な月額はもう少し少なくなります。
「金額と時期」を見える化すると、優先順位が決まる
ここまでの整理で、自分たちの家庭にとって「本当に必要なお金」が、いつ・どれくらい必要なのかが明確になってきたはずです。この情報をもとに、「教育費の準備はこの時期までに集中させよう」「老後資金は長期積立で少しずつ増やしていこう」といった貯蓄の優先順位や方法を考えられるようになります。
ChatGPTを活用することで、金額を1つ1つ電卓で計算する手間も省け、感覚ではなくロジックに基づいた家計設計が実現します。次のステップでは、これらの数字をもとに、どの制度を活用し、どこに預けてどう積み立てていくかの計画を立てていきましょう。
ステップ3:税制優遇制度を活用した貯蓄計画を立てる
― 積立NISA・iDeCoで“賢く貯める仕組み”をつくろう ―
ライフイベントごとの必要金額や積立目安が明確になったら、次に考えるべきは「どの制度や口座を使って、どこにどう貯めていくか」です。
多くの家庭では、貯金といえば「普通預金」がメインですが、それだけでは利息がつかない、インフレに負ける、税制メリットがないという弱点があります。
そこで活用したいのが、税制優遇のある制度(積立NISA・iDeCoなど)。これらをうまく組み合わせることで、「教育資金」「リフォーム費用」「老後資金」など、用途に応じた効率的な資産形成が可能になります。
ChatGPTに、家族の月収や貯蓄可能額を伝えれば、どの制度をどのくらい使い分ければよいかを、目的別にわかりやすくプランニングしてくれます。
ChatGPTへの依頼例(プロンプト)
夫の月収は30万円、妻は10万円で、毎月5万円を貯蓄に回しています。 積立NISA・iDeCoなどの制度を活用して、効率的な貯蓄計画と口座ごとの使い分けを提案してください。
ChatGPTの出力例(目的別の貯蓄計画)
【夫】 ・積立NISA:33,333円(教育・老後資金) ・iDeCo:12,000円(老後資金) ・現金貯蓄:30,000円(介護・近未来のイベント用) 【妻】 ・積立NISA:10,000円(大学資金・リフォーム費) ・現金貯蓄:10,000円(急な出費対応) 【口座別の目的整理】 ・積立NISA:中長期の資金用途に向けた成長投資(教育・リフォーム・老後など) ・iDeCo:老後資金専用(60歳まで引き出せないが、節税メリットが大きい) ・普通預金・定期預金:5年以内に使う資金(介護、教育初期費用など)
「どこに、何のために貯めるか」が明確になる
積立NISAやiDeCoは、「投資」というとハードルが高く感じるかもしれませんが、長期・積立・分散を前提にした制度なので、初心者にも始めやすく設計されています。しかも、非課税のメリットがあるため、同じ金額を貯めても「制度を使うかどうか」で将来の手取り額に大きな差が生まれます。
ChatGPTなら、家族の収入や貯蓄余力に合わせて、無理のない積立額や目的別の口座配分を提案してくれるので、「貯め方が分からない」という悩みも一気に解決。
次のステップでは、支出の側面=保険の見直しを行い、保障と資金のバランスを最適化していきましょう。
ステップ4:ChatGPTに保険の見直しを依頼する
―「万が一」に備えながら、ムダのない保障設計を ―
貯蓄や運用の計画を立てる一方で、見落とされがちなのが「保険の見直し」です。毎月保険料はしっかり支払っているのに、「どんな保障がついているか、正直よく分かっていない…」という方も多いのではないでしょうか。
保障内容がライフステージに合っていなければ、過剰な保険料で家計を圧迫したり、逆に必要な保障が不足していたりすることもあります。
とはいえ、「保険の見直し」は情報も多く、どこから手をつけたらいいか分かりにくい分野。そんなときこそ、ChatGPTを活用すれば、あなたの家族構成や現在の契約内容をもとに、保障の過不足や改善ポイントを客観的に整理するヒントが得られます。
ChatGPTへの依頼例(プロンプト)
現在の保険状況です。見直しポイントがあれば教えてください。 ・夫:生命保険(掛け捨て、死亡保障3,000万円、月1万円) ・妻:医療保険(入院5,000円/日、月5,000円) ・両親の介護費用には備えていません。
ChatGPTの出力例(保険見直しアドバイス)
夫の生命保険:定期型よりも収入保障型のほうが合理的かつ割安になる可能性あり 妻の医療保険:入院1日5,000円では心もとないため、1日1万円+先進医療特約の追加を検討 両親の介護:公的介護保険に加えて、要介護認定に応じた給付のある民間介護保険の併用を推奨 → 保険料の適正化+備えの最適化が同時に実現!
保障と家計のバランスを整えることが、“守りの家計管理”
保険は「何かあったときの安心」を得るためのものですが、入れば安心ではなく、入った後の見直しが非常に大切です。特に、子育て中や親の介護が視野に入る家庭にとっては、「必要な保障」「不要な保障」「優先すべき備え」を定期的にチェックすることが家計の安定につながります。
ChatGPTを使えば、「何が過剰で、何が足りないのか」を対話形式でわかりやすくアドバイスしてくれるため、自分に合った保障をムリなく整えることができます。
次のステップでは、ここまでの内容を総合して、家計全体を見える化する“バランスシート”を作成していきましょう。
ステップ5:ChatGPTに家計のバランスシートを作ってもらう
―「家計の全体像」を見える化して、優先順位と対策を整理する ―
これまでのステップで、ライフイベントの整理・必要資金の試算・貯蓄と保険の見直しを行ってきました。最後のステップでは、現在の家計の状況をひとつにまとめて「見える化」することが目的です。
ここでいう「家計のバランスシート」とは、資産・負債・保障内容の全体像を俯瞰し、将来の目標額と現状のギャップを把握するための一覧表のこと。家計の健康診断のようなもので、現時点での準備状況を冷静に見つめることができます。
ChatGPTに「資産・負債・保障の一覧をまとめて」と依頼することで、過不足や見直しポイントを含めた総合的な分析を行うサポートをしてくれます。
ChatGPTへの依頼例(プロンプト)
資産・負債・保障の一覧をまとめ、家計全体のバランスシートを作成してください。 今後のライフイベントもふまえ、目標とのギャップがあれば教えてください。
ChatGPTの出力例(家計の全体像)
【資産】 ・預貯金:500万円 ・積立資産(NISA・iDeCo):100万円 【負債】 ・住宅ローン残高:2,500万円 【保障】 ・夫の死亡保障:3,000万円 ・妻の医療保障:入院1日5,000円 ・両親:介護保険未加入 【今後の備え】 ・教育資金:あと800万円 ・老後資金:あと2,900万円 ・介護費用:540万円(準備不足) → 現状では「教育資金」と「老後資金」への備えが最優先
全体像を把握すれば、“何をすべきか”が自然に見えてくる
個別の改善だけで終わらせず、資産・負債・保障のバランスを一覧化することで、家計全体の整合性が取れるようになります。そして何より、今やるべきことの優先順位がハッキリと見えてくるのが、このバランスシートの最大のメリットです。
ChatGPTは、ただの質問応答ではなく、あなたの家計全体を俯瞰する“整理役”としても使えるという点で非常に頼もしい存在です。
この最終ステップを経て、将来に対するお金の不安が「行動につながる計画」へと変わるはずです。
まとめ:将来の見通しが立つと、「今」が安心になる
将来に向けたお金の準備というと、「難しそう」「自分にはまだ早いかも」と感じてしまうかもしれません。でも、ChatGPTを使えば、ファイナンシャルプランナーに相談するようなプロセスを、自宅で・気軽に・自分のペースで進められます。
- 何年後に、どんなイベントがあって、いくら必要なのか?
- どの制度を使って、毎月いくら積み立てれば届くのか?
- 今入っている保険は、このままでいいのか、それとも見直しが必要か?
こうした疑問を、あなたの家族構成やライフスタイルに合わせて、対話形式で“かみ砕いて”整理できるのが、ChatGPTを活用する最大のメリットです。
お金の不安は、「わからない」から生まれます。だからこそ、将来の道筋を“見える化”することで、日々の選択や行動に安心感が生まれ、前向きに今を生きられるようになるのです。
次回予告:家計管理とChatGPTの未来
これまでの連載では、支出の分析、資産運用のスタート、ライフプランと保障の設計というように、ChatGPTで実践できる家計管理の手順を具体的にご紹介してきました。
次回はいよいよ最終回。
- AIが家庭の経済管理にどう役立つのか
- どこまで任せてよいのか
- これからの時代に求められる家計リテラシーとは何か?
を、実践知とともにまとめてお届けします。
▶ 次回記事:
「ChatGPTで家計管理を劇的に改善! :AI時代の家計管理と、これからの“賢い選択”とは?」
ChatGPTと一緒に築く、新しい家計管理のカタチ。その未来像を、あなたもぜひ体感してください。
「注記」
▶ ChatGPTの活用方法について: ChatGPTは生成AIであり、投資助言や金融判断を行うものではありません。対話結果はあくまで参考の一例とし、最終的な判断はご自身または専門家と相談のうえで行ってください。
▶ リスク許容度の診断について: AIによるリスク診断は、限定的な情報をもとにした一つの見解に過ぎません。実際の投資判断には、家計全体の見直しや専門家のアドバイスが不可欠です。
▶ 商品例・制度活用の説明について: 本文中で紹介している商品・制度例は一例であり、特定の金融商品を推奨するものではありません。投資信託やiDeCoの商品選択には、それぞれのニーズや制度条件を確認のうえでご利用ください。
記事中のChatGPTによる出力は、あくまでも一例であり、入力状況によって全く同じ出力結果が得られるわけではありません。また、出力結果において個別金融商品が出力される場合がありますが、弊オフィスとは一切関係なく、またこれを推奨するものではありません。
(執筆:ファイナンシャルプランナー 平野 泰嗣)
この記事を読んで、家計の見直しに興味を持たれた方は、LFCにお問い合わせください。LFCでは、家計の現状分析や目標設定、資産運用や保険の提案など、あなたのライフプランに合わせた家計の見直し相談を行っています。
私たちは、あなたの幸せな人生を実現するためのパートナーとして、全力でサポートします。FPによる家計見直し相談に興味を持たれた方は、ぜひFPオフィスLife & Financial Clinicの「トライアル相談(初回面談)」をご利用ください。トライアル相談では、お客様のお金の悩みや目標に対して、簡単なシミュレーションとアドバイスを提供します。